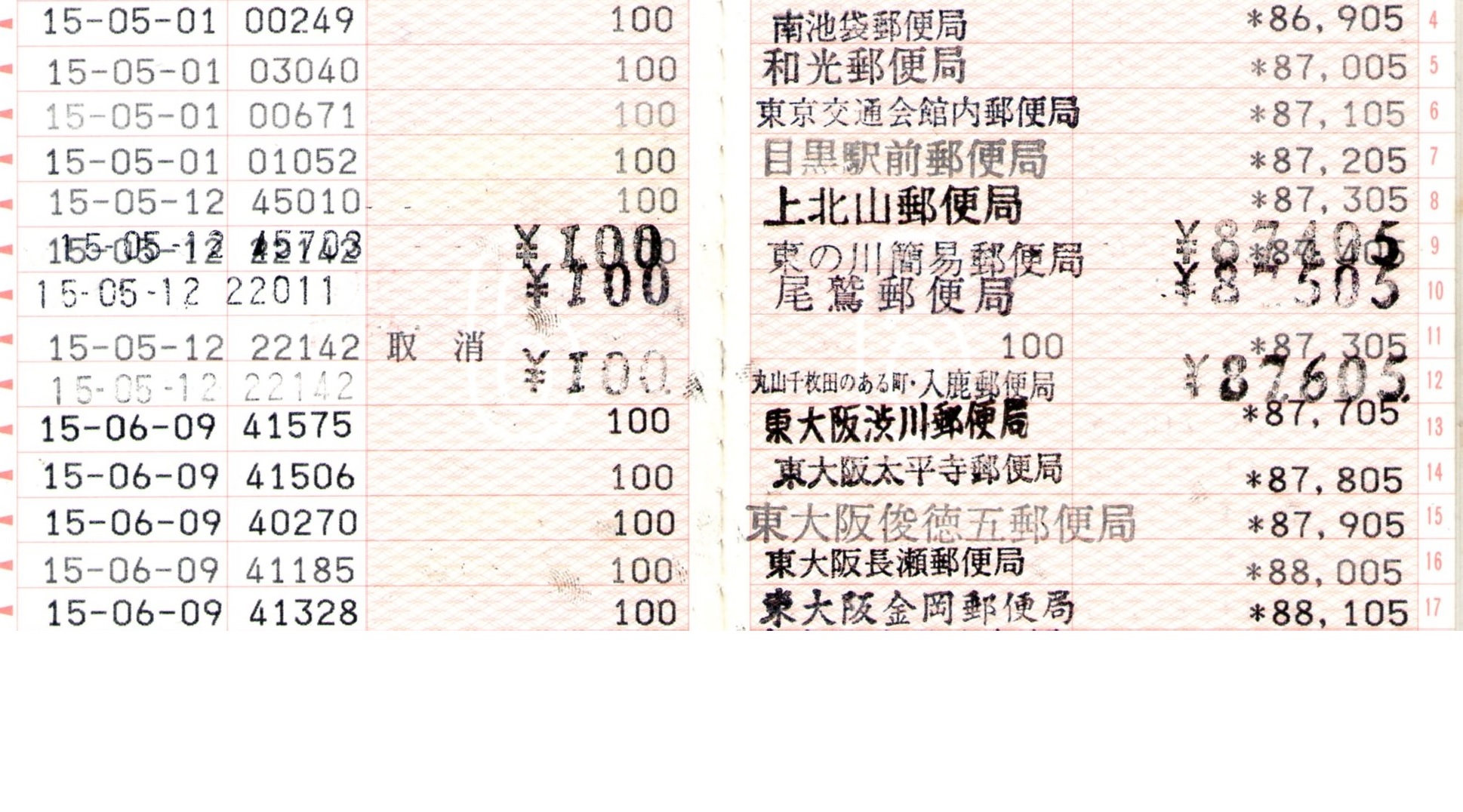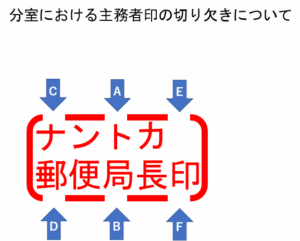鉄道などで郵便局を回る際に、フリーきっぷというものはとても便利です。自由に乗り降りできるというのがなんと言っても強みです。普通の旅行と違って、各駅で降りて目的地に行く必要がありますから。
ところが、フリーきっぷというのは観光目的で発売されるものが多く、そのため行動範囲が観光エリアに限定され、しかも土休日しか使えないものもあります。大都市の公営交通ならビジネスユース目的の1日乗車券もあるんですが。
「○○フリーきっぷ」とか「1日乗車券」という名前ならほぼアタリです。ですが、中には「○○ホリデーパス」というのもあり、これは土休日しか使えないのでハズレです。フリーきっぷという名前でも、土休日に利用が限定されているものがあるので注意が必要です。関東地方で言うと、北総鉄道(期間限定)、関東鉄道、千葉都市モノレール(時間制限付きで平日利用なきっぷあり)のきっぷが土休日限定となります。地方だとこのパターンが結構増えるので大変です。ただ、土休日以外に指定の期間(夏休みなど)は連日使えるものもあり、それは何とか利用可能です。便利なきっぷのページでもそんなきっぷを紹介しています。
もう1つ、ちょっと不満というんでしょうか、言いたいこともあります。それは、平日と土休日で料金が違う!という場合があること。仙台市営地下鉄(全日用840円、土休日用620円)とか、大阪メトロ(平日800円、土休日600円)はそのパターンです。あえてOsaka Metroではなく大阪メトロって書いてるのはささやかな抵抗です。
フリーきっぷと一口に言っても、会社線の全線乗り放題のもの(これが理想)と、指定のエリアだけ乗り放題(これが現実?)に分かれます。ただし、指定エリアで利用できるきっぷは、複数の会社線にまたがって利用できるものが多いので、その点は有利かと思います。旅程に合わせて選ぶ、というよりむしろきっぷのエリアに行程を寄せるというのが現実的な行動でしょうか。究極のフリーきっぷ(?)青春18きっぷだけでなく、各社のフリーきっぷを駆使して回れるところを回りきる、それが腕の見せ所なのかもしれません(無責任発言)。
変わり種、むしろ裏技に近いかもしれませんが、1日乗車券として単独で発売されるのではなく、お食事券付きのセットで発売されるきっぷもあります。以前は東武鉄道(東上線)で、今は福井鉄道で発売されています。お食事券の対象メニューの料金と、1日乗車券(平日用)の料金の推測値からお得感がありそうに思えたので(あくまでししょーの私見です)、こちらも紹介しています。行程によってはお得になるかもしれません。あくまで参考ですので、よろしければご検討ください。