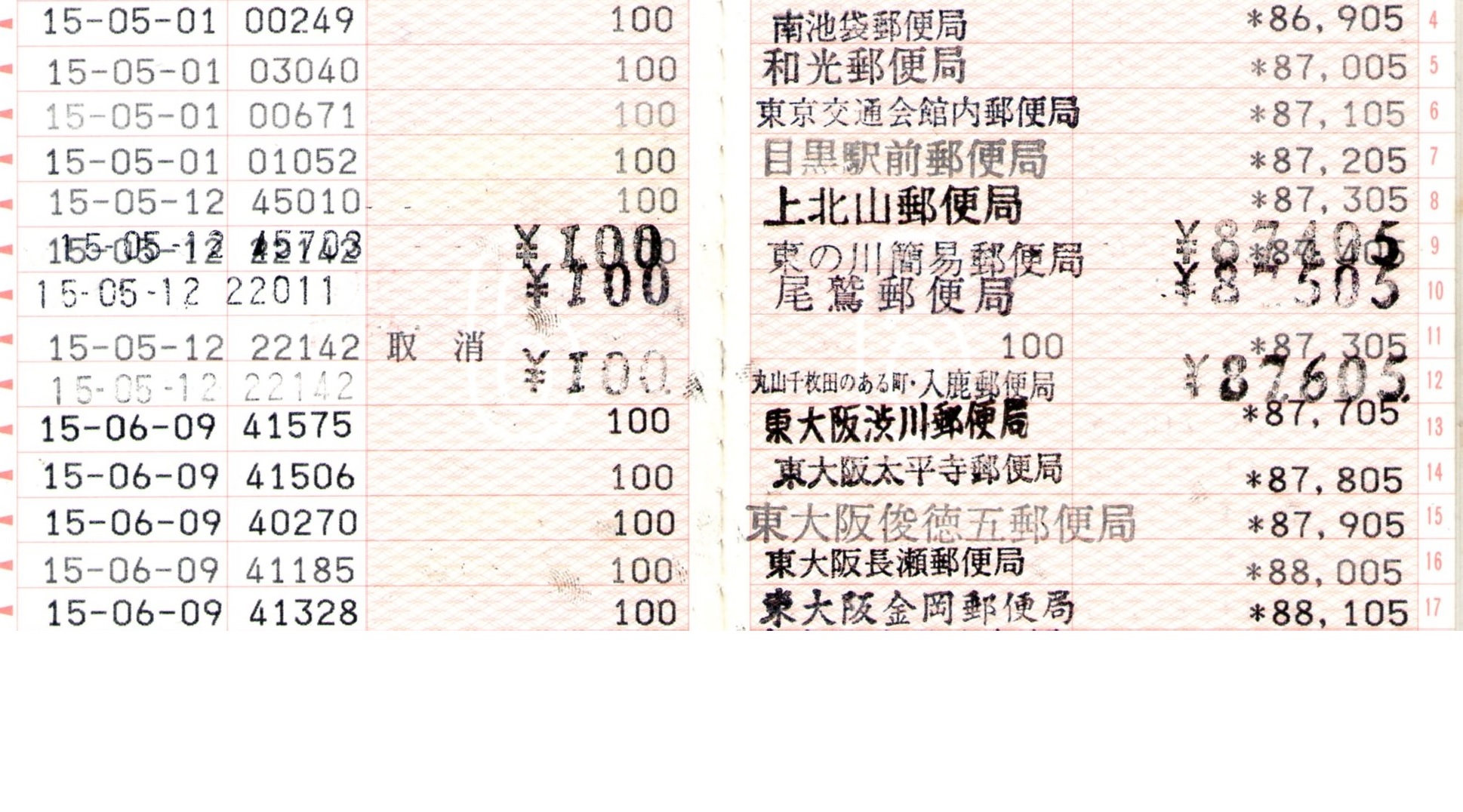バスで郵便局を回る方法については、過去何度か書いてきました。ですが、あくまでバスは不確定要素なので、推奨はしていません。とは言え、都市近郊においてはどうしてもバスに頼らざるを得ない場面もあります。今回は、これまでの試行錯誤で見えてきたバス利用の方法についてまとめたいと思います。
なお、ここでは都市近郊におけるバス利用について述べていきます。都市近郊以外の地方部では、ほぼ1本のバス系統しかなく、迷う要素がありませんので、ここでは触れないことにします。
1.対象の訪問局をピックアップする
まずは、対象地域(行きたいところ)の郵便局の所在を確認します。闇雲にバスに乗るのは効率が悪いので、ルート決定のためには必要な行程です。また、ししょーみたいにとりあえず鉄道で行けるところを行き尽くして、残りをバスで拾うパターンの場合は、訪問局が点在するので、事前チェックは必須になります(ダブり回避のためです)。
2.最寄りのバス停を調べる
行きたい局が確定したら、NAVITIMEなどのツールを使って局へのアクセスができるバス停を探します。また、そのバス停を通るバス会社も同時にチェックします。この後の系統選定において重要になりますので。局の直近にバス停がない場合は、アクセスしやすいバス停を探しましょう。直線距離が近くても、途中に山があったり、川に橋が架かってなかったりする場合があるので、要注意です。マピオンのルート検索などを活用しましょう。
3.路線図からバス停を探す
会社ごとにバス停を分類したら、バス路線図から該当のバス停を探します。これは結構面倒な作業ですが、必要な作業ですので根気よくやりましょう。バス路線図は都市近郊を走る会社であれば、必ず公式サイトで公開されています。PDFファイルで提供されることが多いので、ぜひダウンロードしておきましょう。また、バス会社によっては違う場所に同一名称のバス停が存在することがありますので、どの地域(営業所)のバス停であるかも忘れずチェックしましょう。案外ハマりやすいワナだと思います。
※国際興業バスを例に取ると、北町一丁目(練馬区、蕨市)、北町三丁目(練馬区、蕨市)、区界(北区赤羽北・板橋区小豆沢、板橋区加賀・北区十条台)、幸町一丁目(朝霞市、川口市)、桜ヶ丘(朝霞市、川口市)、市民医療センター(戸田市、さいたま市)、市役所前(さいたま市、川口市、飯能市)、新町(練馬区、川口市)、浅間神社(さいたま市、川口市(鳩ヶ谷))、第二中学校(蕨市、新座市)、団地南(足立区、さいたま市)、中央通り(板橋区、飯能市)、天神橋(川口市、飯能市)、中郷(足立区、飯能市)、仲町(板橋区、飯能市)、氷川町(板橋区、戸田市、草加市)、本町四丁目(さいたま市、戸田市)、本村(さいたま市南区、桜区)、南町(板橋区、川口市、戸田市)、峯(川口市、飯能市)、向原(川口市、さいたま市)、領家一丁目(川口市、さいたま市)、領家二丁目(川口市、さいたま市)、六間道路(川口市、さいたま市)、随分多いですね。。。
4.バス系統を決定する
行くべきバス停が決まったら、そこを通るバス系統をチェックしましょう。効率よく回れる系統(多くのバス停を通る系統)を見つけて、それを軸にするのも良いと思います。ですが、ちょっと注意事項が。系統によっては、本数が少ないものもあります。日中1時間に1本程度なら、ギリギリ許容範囲です。中には、朝夕ラッシュ時(~8時台、19時台~)のみの運転、さらには早朝または深夜のみ運転の系統(出入庫系統など)もありますので、当然それらは使えません。我々の活動時間である9~16時に動いていないバスは意味がありません。
5.系統が分かったら、それを元にプランを考える
乗るべき系統が決まったら、具体的なルートを決めましょう。基本的にバスの1日乗車券を使うことになると思いますが、交通費をケチって家から近いターミナル駅からバスに乗ろうとすると、意外に時間がかかって効率が悪くなるので、ここはおとなしくスタートの郵便局の近くまで電車で移動しましょう。一旦バスに乗ったら、あとはなるべくバス路線だけでつなぐルートでよいと思います。ただし、乗りたいバス系統につながる路線がない、あまりに移動が長すぎるなどバス利用が難しい区間は、電車でつなぐのも1つの手です。ついでにトイレ、食事休憩もできますので。
その他の注意事項としては、時間をあまりシビアに決めないことでしょうか。バスは道路状況などにより遅延することも多いですし、ただバスに乗って移動するわけではないので、郵便局での手続きに時間がかかると、せっかく組んだ完璧なプランが破綻してしまいます。あくまで、ルートだけ決めてどの時間のバスに乗るかは決めないほうがよいと思います。
サイト内で時々、バスは不確定要素だから(ryとか書いてますけど、全く使うなと言う意味ではなく、必要に応じて活用してもよいと思っています。ですが、あくまで不確定要素ですので、無理をせずのんびりバスの旅を楽しんで欲しいと思います。うん、説得力がないな。