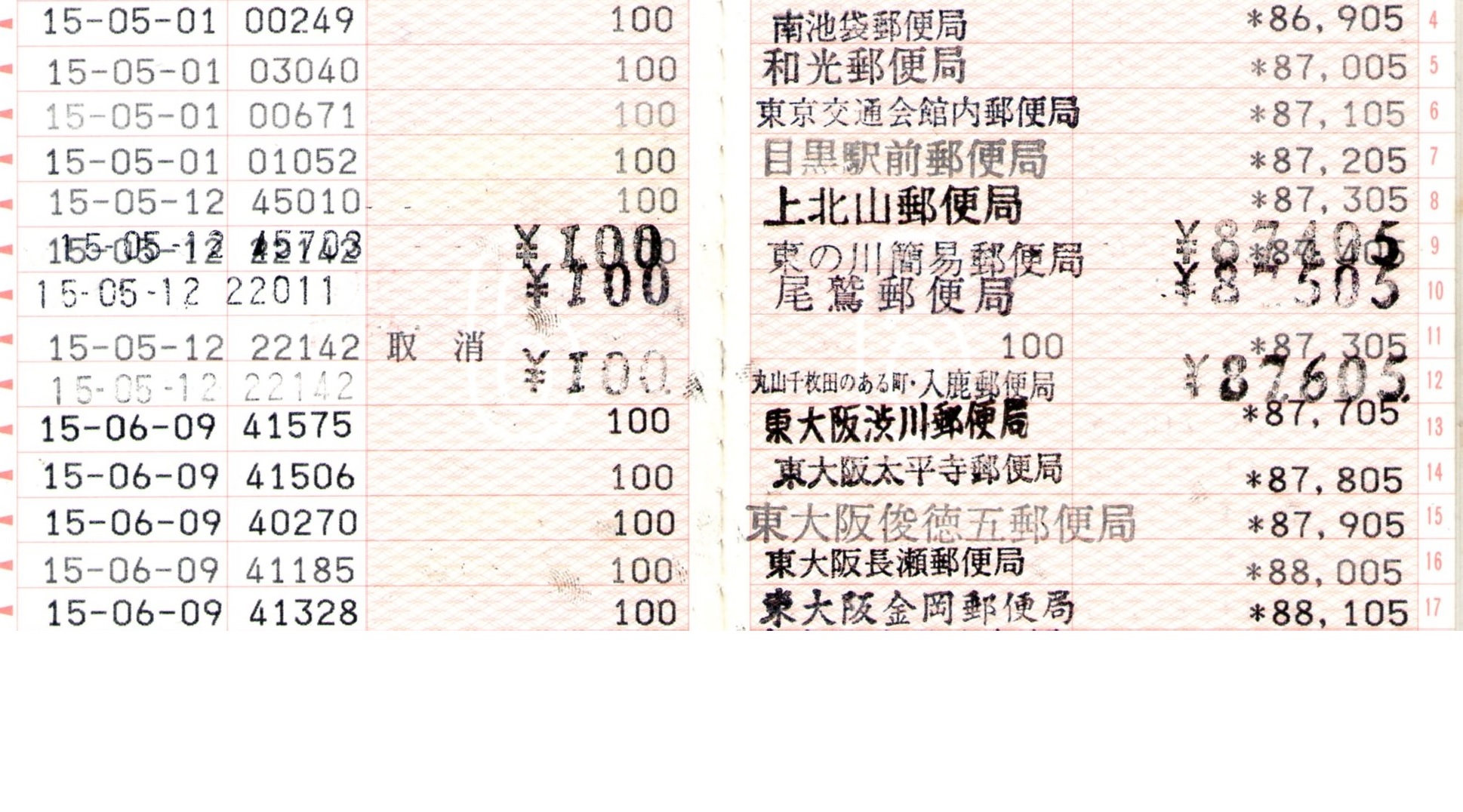なんか堅苦しいタイトルになってますけど、このサイトは旅行貯金をテーマにしています。基本的には鉄道をベースに回りたいのですが、場合によっては鉄道の走っていない地域を訪問することもあります。その場合、当然バスを利用することになるわけですが。
都心や市街地を走るバスは、1時間に数本以上(10分間隔以内)で頻繁にやって来ますが、郊外ではそんなに人もいないので1時間に1本程度、さらに利用者が少ない地域は2時間に1本、さらに人のいない過疎地域においては1日3本とか4本という場所もあります。
それでもバスが走っていればいいのですが、最近そんなバス路線が廃止される事態が起きています。バス路線が廃止になることは今までからありましたけど、特に昨今は2024年問題により運転手の不足が深刻になり、そこそこ利用者が見込める路線でさえも廃止される状況になってきました。
とは言え、ある程度の利用があって必要とされているバス路線なら簡単には廃止にならないものです。バス会社から発表される路線廃止のお知らせを見ていると、やはり過疎地域(国土交通省がそう呼んでいるので、その呼び方を踏襲しています)の路線が目立ちます。大都会の駅前で頻繁にやってくるバス路線が廃止になるなんてことはまずないです。
過疎地域のバス路線を見ていると、だいたい似たような特徴があります。住んでいる人が少なく、住民はほぼマイカーを利用しており、バスを利用するのは学生かお年寄りが多い。かつて多く存在したいわゆる赤字ローカル線も晩年(廃止前)は学生とお年寄りばかりが車内で見受けられました(そして半分以上の乗客は鉄ヲタです)。
客の乗らないバスを運行してもコストは掛かります。収入が少なければ当然赤字になりますし、それが会社の経営を圧迫するなら廃止にしようということにもなります。ただ、少ないとは言え利用者がいるバスをいきなり廃止するということはありません。利用しているバスが明日から走りません、と言われたら困ります。
ではどうするかというといくつかパターンがあります。1つ目はコミュニティバスを運行すること。これは民営のバス会社ではなく自治体が主体となって運行するものです。もちろん自治体がバス運営のノウハウを持っているわけではないので、近隣のバス会社または元運行会社に委託して運行する形になります。コミュニティバスとか自主運行バスと書いてあればそのパターンになります。
さらに利用者が少ない場合は、バスではなく乗り合いタクシーという形を採ることもあります。タクシーと言ってもいわゆるセダンとかJPNタクシーみたいなのではなく、ある程度のキャパを持つワゴン車です。これは地方だけでなく、意外にも市街地(例えば東京の葛飾区)でも運行されています。ちなみに葛飾区のものは『地域乗合ワゴンさくら』という名前です。
さらに利用者が少ない場合、予約制となります。デマンドバスという言い方が一般的でしょうか。つまり、毎日運行ではなく利用したい人が利用日前日までに乗降停留所を指定して申し込みます。すると、その区間だけ運行してくれます。ほとんどタクシーみたいな感じですが。なお、運行時刻は決まっていることが多いです。
それよりももっとひどい場合は、本当にバスがなくなります。どこかへ移動するなら知り合いのクルマに乗せてもらうか、デイケアサービスの送迎でも使ってくれという状態です。学生さんなら全寮制の学校に行くか、学校の近くに下宿するパターンです。
さて、郵便局巡りの話に戻りますが、過疎地域のバス路線が廃止になり、コミュニティバスやデマンドバスなどに転換した場合、どういう影響があるでしょうか。コミュニティバスは基本的に1時間1本程度です。場合によっては2時間に1本。ひどいのは1日2本てのもあります。それでも乗れるだけマシです。地域によってはそのエリアの住民または通勤、通学者に限定するなんてのもあり、そうなると部外者は利用できません。ハイヤーていくらするんだ?
ししょーは過疎地域バス路線の研究家ではないので、全国のバス事情を把握しているわけではありません。ですので見聞したいくつかの例を挙げたいと思います。コミュニティバスに関しては運営元が変わっただけで、実態は変わりないものと見なします。
和歌山県伊都郡高野町には2つの郵便局があります。1つは高野山の門前町にある高野局、もう1つは富貴エリアにある富貴局です。富貴方面にはかつて五條バスセンター(奈良県)から東富貴バス停までの奈良交通バスが運行されておりました。なお、富貴局の最寄りバス停は富貴診療所前です。このバスが廃止になる際に、『ゆめたまご・ハイランドタクシー』という乗合タクシーが五條イオン前(五條バスセンターとほぼ同位置)から東富貴バス停を経由してその先の下筒香集会所前バス停まで運行されるようになりました。しかも便数が増えてる!これはレアケースだと思いますが。
大阪府豊能郡能勢町(大阪府の左上の出っ張り)にもいくつか郵便局があります。こちらはかつて能勢電鉄の妙見口駅から奥田橋バス停まで走る阪急バスの循環系統がありました。この沿線に地黄局前バス停、歌垣局前バス停というのがあり、それぞれ地黄局、歌垣局に行けたのですが、このバスは2024年3月に廃止されてしまいました。昔乗った時は奥田橋循環が1時間に1本程度、うち2本が能勢営業所に近い今西バス停まで走っていました。後に今西行きは能勢町宿野(町役場の近く)行きになり、便数も大幅減(9時台、12時台、13時台しか使えない)、歌垣局前バス停は循環のループ上にあるので行って来い(折り返しのバスで帰ること)も難しい状況でした。
今さら遅いのですが、妙見山を訪れた時こっちに気付いていればねえ。ただ、能勢電鉄のフリーきっぷもなくなったので、ここは究極の選択だったかも。
そしてバスの廃止と共にほぼ同じルートで『妙見口のせ号』という乗合タクシーが運行されるようになりました。が、しかし、利用できる方:能勢町民及び能勢町への通勤・通学者がご利用いただけます。だと!?ヲワタ\(^_^)/でも誰でも利用できるようにしたらハイカーの餌食になるのかも。妙見口駅から地黄局でも6km以上の距離があります。妙見口駅からタクシーを呼ぶしかないか。
さて、神奈川県の奥深く(?)相模原市緑区でも神奈中バスの系統が廃止されるというアナウンスがありました。代替手段については検討中とのことですが、この辺りも山登る人が多そうだな。八07系統(八王子駅北口~相模湖駅)では実際にデカいリュックを背負った人が途中で降りていったし。これだと今のバスが廃止になって乗合タクシーなどに代わった場合、住民と関係者以外利用できないなんてことにならないか、心配になります。
余計なことを考えるよりも廃止前に乗っておいた方がよい。と思い立ち、こちらのバスを利用するプランを前倒しで進めることにしました。神奈川県に関しては、全局制覇を目指しています。実は県西部に関してはまだ精査できてないので、他にも不安なところはあるのですが。なお箱根町についてはクリアしています。
これからもバス路線の縮小、廃止を気にしながら旅が続くのでしょうか。ただ、神奈川県以外については行ける範囲で行くことにしているので、そんなに気にしなくていいかも。ですが、地域交通の行く末には関心と問題意識を持って引き続き注視したいと思います。