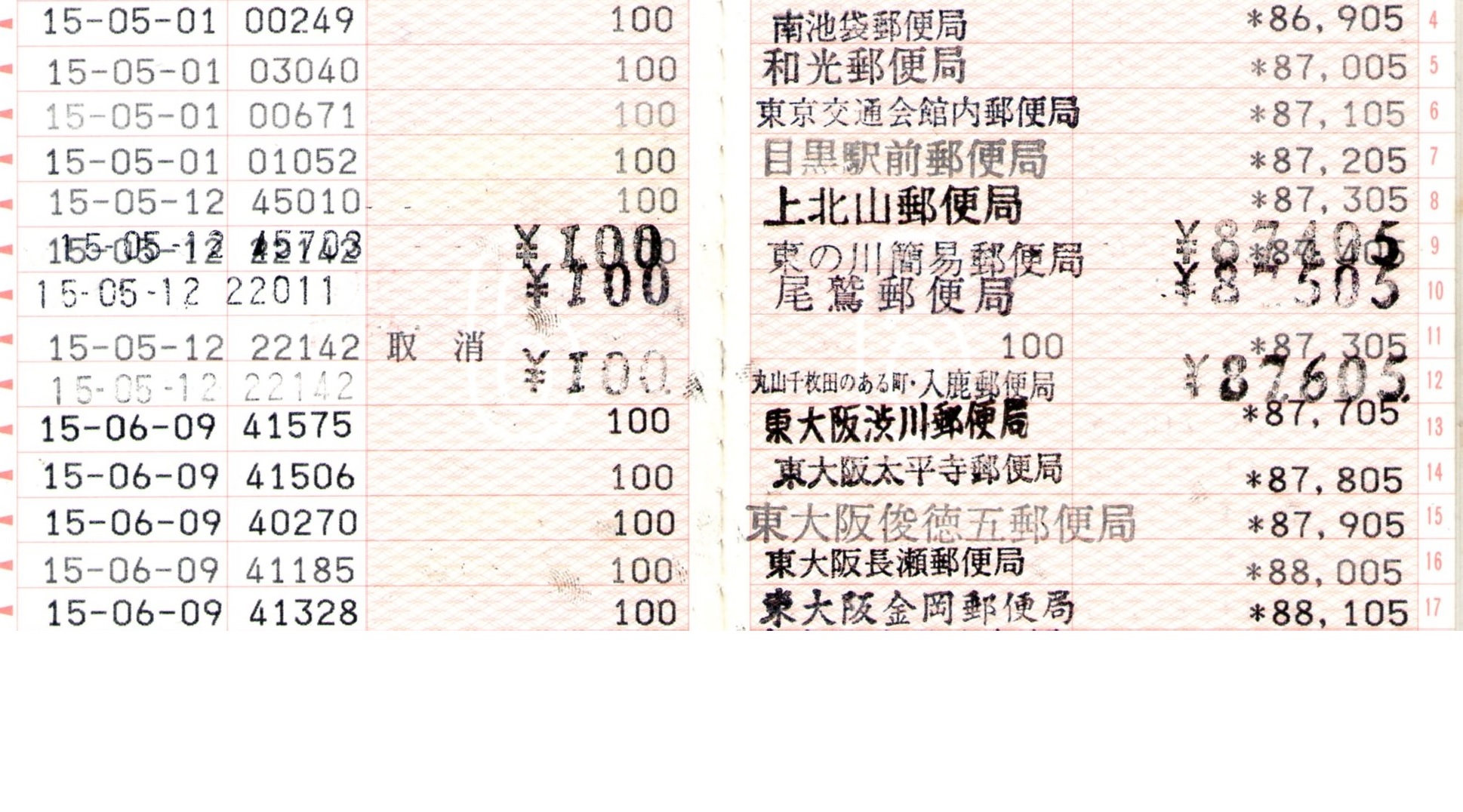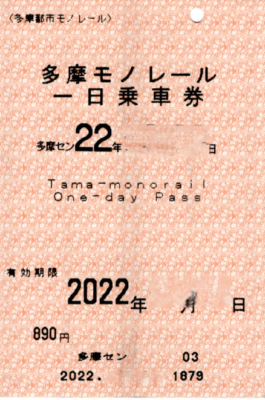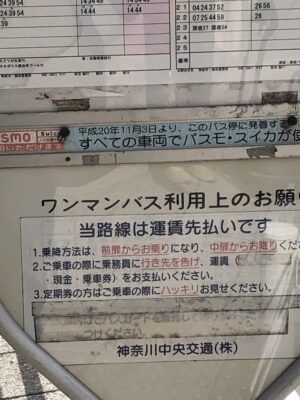SDGs。そんな言葉が最近流行っていますね。それはもうウザイくらいに。何だっけ?Sustainable Development Goalsか。17個ぐらいゴールがあるらしいんですが、そこまで考えるのも大変なので考えませんけど、旅行貯金的なSDGsというものを考えてみました。すなわち、S(それなりに頑張れば)D(どーにかなりそうな)G(ゴール)ということで、現実的な目標を考えてみました。
このサイトのどこかで、目標は全国の24000局です、などと嘯いておりましたが、当然そんなのは到達不能なものだと思われますので(ついに言っちゃった)、現実的な目標と言いますか、限界はどこなのか考えることにします。
時間とお金をかけて全国どこでも行けるのなら、泊まりも込みで制限はないと思いますけど、泊まりが発生するものはイレギュラーなパターンと考えれば、だいたい日頃の行動範囲は、日帰り旅行として朝早く家を出て目的地(出発地)に9時前ぐらいに到着できるところになると思います。局数にこだわらなければ、出発地に到着するのは10時ぐらいでもいいかもしれません。とにかく、活動できる時間は9時~16時(一部大規模局や時差営業局は17時まで)ですので、帰りの時間は考えないものとします。
東京を朝7時ぐらいに出るとすると(それ以上早起きするのは難しいです)、各方面に普通列車で移動し、だいたい9時頃遅くても10時頃に到着できる所が出発地となります。新幹線を使うと劇的に早くなる場合もありますが、値段が高い、青春18きっぷが使えないなどの事情により、ここでは考えないことにします。あくまで普通列車(各停ではなく)で移動するものとします。2022年3月改正ダイヤをベースに算定していますが、関東エリアにおいてはそれほど大きく変わることはないと思います。
1.東海道線方面
9時前までという条件なら根府川までは行けます。10時前という条件にすれば吉原辺りまで行けますね。伊東線方面では、伊東駅到着が10時を少し越えるので伊東線内なら何とか範囲内でしょうか。
2.千葉方面
千葉は楽勝なのでもう少し先を考えます。内房方面では、木更津には9時前に到着できますが、その先の浜金谷方面の列車が9時過ぎまでありません。10時前に到着できるのは佐貫町となります。外房方面だと、9時前に到着できるのは茂原まで、10時前まで許容すると勝浦までは行けます。
さて、銚子方面ですが、9時前に佐倉まで行けます。総武本線方面では10時前なら飯岡まで行けますね。成田線方面なら滑河まで。銚子方面については問題なさそうです。
3.常磐線方面
次は常磐線方面。特急ひたちもありますが、考えないことにします。9時前の到着なら、上野乗り換えで石岡まで行けます。10時前の到着を考えると大甕(おおみか)まで行けますね。蛇足ですが、水戸から水郡線方面、勝田からひたち海浜鉄道方面は10時まで接続列車がありません。大洗鹿島線方面は、大洗までならなんとか10時までに着けそうです。
4.宇都宮線方面
宇都宮線に沿って北上する場合、途中湘南新宿ラインに乗り換えれば9時前に自治医大まで行けます(自治医科大学内簡易局があります)。10時前なら岡本まで行けますね。小山乗り換えで両毛線方面は佐野まで(乗り換えの問題です)、水戸線方面は稲田まで行けます。ひみつの平日パス(休日おでかけパスの平日版、不定期発売)の範囲は十分回れます。
5.高崎線方面
高崎には届かなかったですが、9時前なら神保原まで行けます。10時までなら高崎をオーバーするのでその先まで考えましょうか。信越線横川にはギリギリ10時前に着けます。軽井沢駅行きのJRバスは10時以降の発車です。上越線は渋川まで、吾妻線は11時過ぎまで接続列車がありません(T_T)両毛線方面は前橋までとなります。
6,中央線方面
順番がおかしいですか?最後に中央線方面を考えます。9時前であれば藤野まで行けます。日連局はかなり遠いですが。10時前であれば山梨市まで行けます。甲府を過ぎると格段に列車本数が減るので、そこが壁になりそうですね。
そうか、分かったぞ!東海道線ツアーの限界は吉原スタートだったのか(今さらかよ)。と言うことは頑張っても静岡ぐらいまでしか行けないんですかね。まあ、確かに浜松辺りを回る時は新幹線必須だったし。
と、なんだか方向性が見えてきたので(ホントかよ?)これからの目安にしようかなと思います。と言うわけで持続可能な局めぐ目標に向けて頑張っていきましょう(雑なまとめ)。